BLOGブログ

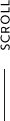

手湿疹は、手の皮膚が乾燥し、赤みやかゆみ、ひび割れを起こす慢性的な皮膚炎です。家事や仕事での水仕事、アルコール消毒などが原因となり、症状を繰り返す人も少なくありません。見た目や痛みだけでなく、日常生活や仕事に支障をきたすこともあるため、原因に応じた治療と正しいスキンケアが欠かせません。ここでは、実際にどのようなメカニズムで手湿疹ができるのか、その診察や治療、予防のためのスキンケアなどをご紹介します。
手湿疹(てしっしん)は、手の皮膚に炎症が起こる慢性の皮膚疾患です。
手のひらや指先、手の甲などに赤み、かゆみ、乾燥、ひび割れ、小さな水ぶくれなどが現れ、悪化すると痛みや出血を伴うこともあります。
「主婦湿疹」「手荒れ」と呼ばれることも多く、誰にでも起こりうる身近な病気です。
日本では、特に水仕事やアルコール消毒を頻繁に行う人に多く見られます。
美容師、調理師、医療従事者、清掃員など、手を酷使する職業では発症率が高く、長期間の治療が必要となることも少なくありません。
手湿疹は一度発症すると再発を繰り返しやすく、生活の質(QOL)を大きく損ないます。
原因や症状は人によって異なり、刺激性、アレルギー性、アトピー性など、複数のタイプが重なっている場合もあります。
そのため、正確な原因を特定し、適切なケアを続けることが重要です。
手湿疹の原因は、大きく分けて外的要因と内的要因に分かれます。 水・洗剤・アルコールなど外からの刺激だけでなく、ストレスやホルモンバランスなど身体の内側からも影響を受けます。
-scaled.jpg)
最も多いのが、洗剤や石けんによる刺激です。 手の甲に洗剤が繰り返し触れることで皮膚のバリア機能が壊れ、ブツブツとかゆい湿疹ができることがあります。
手洗いや水仕事を繰り返すことにより皮膚のバリア機能が破壊され、角層の水分が失われやすくなります。これにより皮膚が乾燥し、ひび割れや炎症が起こります。
また、ゴム手袋・金属・香料・防腐剤などが原因となるアレルギー性接触皮膚炎もあります。これらの物質に対して免疫が過剰に反応し、炎症を引き起こします。仕事で特定の薬品や洗剤を扱う人は特に注意が必要です。
洗剤・石けん・シャンプーなどの化学的刺激
→ 繰り返し使うことで皮膚の油分が奪われ、バリア機能が低下します。
水仕事や頻繁な手洗い
→ 皮膚の水分が蒸発し、乾燥やひび割れを引き起こします。
アルコール消毒剤の使用
→ 揮発性が高く、角層を乾燥させやすい。
金属・ゴム・香料・防腐剤などのアレルゲン
→ アレルギー反応を起こし、炎症を伴う湿疹を生じます。
気候や環境
→ 冬の乾燥・寒冷、職場の空調なども皮膚刺激の原因になります。
-scaled.jpg)
ホルモンやストレスの影響で自律神経が乱れると、皮脂分泌が減少し、皮膚の防御力が低下します。 その結果、手の甲や指先にかゆみを伴うブツブツが出やすくなります。
アトピー素因を持つ人は、皮膚の構造自体が弱く、フィラグリン遺伝子異常などにより角層の保湿力が低下しています。そのため、軽い刺激でも炎症を起こしやすく、症状が慢性化しやすい傾向にあります。
アトピー素因
→ 生まれつき皮膚のバリア機能が弱く、外的刺激に敏感なかたに起こりやすいです。
フィラグリン遺伝子異常
→ 皮膚の保湿に関わるタンパク質が不足し、乾燥しやすいため手湿疹が起こります。
免疫バランスの乱れ
→ 免疫バランスが崩れると、アレルギー反応を起こしやすく、炎症が慢性化しやすいです。
ホルモンやストレス
→ 自律神経の乱れや皮脂分泌の低下が影響することもあります。
手湿疹は誰にでも起こりうる湿疹であり、体質的に皮膚が弱い人や、免疫が過敏に反応する人は発症しやすい傾向があります。
手湿疹の発症は、「皮膚バリアの破壊 → 水分蒸発 → 角層の乾燥 → 炎症反応」という連鎖で進みます。
健康な皮膚の表面は「角層」と呼ばれる層で覆われており、外からの刺激やアレルゲンを防ぐ「バリア機能」、皮膚の水分を保つ「保湿機能」を担っています。この角層には、皮脂・天然保湿因子(NMF)・セラミドが存在し、皮膚を守る膜のような働きをしています。
しかし、次のようなバリア機能が低下します。
といった刺激が続くと、この保護膜が破壊されてしまいます。結果として、皮膚のバリアが壊れ、外からの刺激に非常に敏感になります。
バリア機能が壊れた皮膚には、通常なら防げるはずの洗剤・金属・香料・化学物質などが簡単に入り込みます。これらの物質が皮膚の中の免疫細胞に認識されると、炎症性サイトカイン(IL-4、IL-13、TNF-αなど)が放出され、炎症反応が始まります。
このとき皮膚の内部では、以下のような反応が起こります。
炎症によって神経が刺激され、強いかゆみが生じます。 かくことで一時的に楽になりますが、皮膚をさらに傷つけてブツブツや炎症が広がり、手の甲や指の間にも広範囲に症状が出ることがあります。とくに手の甲にブツブツとした湿疹が現れ、「見た目が気になる」「衣服が擦れてかゆい」と訴える方も多くいます。また、ストレスや睡眠不足が続くと、この悪循環がより強くなります。
「炎症 → かゆみ → 掻く → さらに炎症」悪循環(itch-scratch cycle)が続き、湿疹が慢性化します。
炎症が長く続くと、皮膚は刺激に耐えようとして角層を厚くします。これが「角化(かくか)」と呼ばれる反応です。
皮膚が硬くなり、ひび割れや痛みが生じ、見た目にも白く粉を吹いたようになります。特に手の甲の皮膚は乾燥しやすく、季節の変わり目やストレスによってかゆい症状が悪化することもあります。 炎症が強い時期には水疱(汗疱型手湿疹)が出たり、皮膚がじゅくじゅくしたり、ブツブツとした湿疹が広がるケースもあります。
このように、手湿疹は単なる「乾燥」ではなく、皮膚の防御機構が崩壊した結果、免疫反応が暴走している状態といえます。
手湿疹にはいくつかのタイプがあります。それぞれの特徴を理解することで、自分の症状に合った治療や予防が行いやすくなります。
最も一般的なタイプです。長時間の水仕事や洗剤の使用により、手の甲や指先が乾燥し、ブツブツとしたかゆい湿疹が出ることがあります。かゆみは軽度でも、掻き壊すとブツブツが広がり、皮膚が硬く厚くなります。主婦や調理職、美容師に多く見られます。
特定の物質に対して免疫が反応して起こる湿疹です。金属(ニッケル、クロムなど)、ゴム手袋の成分、香料、防腐剤などが原因となります。水ぶくれや強いかゆみが特徴で、原因物質の除去が治療の鍵です。パッチテストで陽性となる場合が多いです。
ー性皮膚炎の既往がある人に多く、バリア機能の低下と免疫反応の異常が関係しています。 症状は長期化しやすく、季節の変わり目やストレスで悪化する傾向があります。特に手の甲のぶつぶつやブツブツがかゆいと感じたら、早めの受診が大切です。
手のひらの皮膚が厚く硬くなり、深いひび割れを伴います。かゆみよりも痛みが強く、治りにくいのが特徴です。
初夏から秋にかけて多く見られ、指の側面や手の甲、手のひらに小さな水ぶくれ(汗疱)が出ます。 破れるとかゆい炎症とともにブツブツした湿疹が広がることもあります。 ストレスや季節の変化、発汗の増加などが誘因となり、悪化するケースも少なくありません。 ※手足の水虫と間違えられる場合もあります。

当院での手湿疹の診断は、皮膚科医による問診と視診を中心に行われます。
発症の時期、職業、手洗い・手袋の頻度、使用している化粧品や洗剤の種類を詳しく確認します。職業性であるか、家庭環境で悪化しているかも重要な手がかりになります。
皮疹の形や分布、左右差などを観察します。アレルギー性を疑う場合にはパッチテストを行い、原因物質を特定します。
また、白癬(手の水虫)との鑑別のために真菌検査を行うこともあります。血液検査ではIgE値や好酸球数を測定し、アトピー素因の有無を確認します。
乾癬(かんせん)、掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)、貨幣状湿疹(かへいじょうしっしん)、白癬(はくせん)など、似た症状を呈する疾患を除外することが大切です。
手湿疹の治療は「炎症を抑える」「皮膚を守る」「原因を避ける」という三本柱で行います。
以下のような薬が使用されます。
炎症を抑える主力治療薬です。
症状の重さに応じて強さ(ランク)を調整し、医師の指示に従って使用します。
手のひらなど角質が厚い部分にはやや強めの薬を使うことがあり、改善後は徐々に弱い薬に切り替え、再発を防ぎます。
乾燥を防ぎ、皮膚のバリア機能を回復させます。
ワセリン、ヘパリン類似物質、セラミド配合クリームなどが代表的です。
入浴や手洗いの直後に塗ることで効果が高まります。
かゆみを軽減するために内服します。夜間の掻破防止にも役立ちます。
※かゆみも深刻な症状の1つです。我慢せずにかゆみの有る場合にはその旨を医師にお申し出ください。
重症例では免疫抑制外用薬(タクロリムス軟膏)や光線療法を行うこともあります。
症状が強い場合は短期間の内服ステロイドで炎症を鎮めることもあります。
※医師の指導の基に薬の使用は行われます。何かご心配の場合には医師や看護師におたずねください。
薬の効果を維持するためには、日常生活での工夫が欠かせません。
これらの工夫が、薬だけでは防げない再発を抑える鍵になります。
手湿疹を治療する上で、セルフケアは非常に重要です。日常の行動を少し変えるだけでも、皮膚の回復力が大きく向上します。例えば、以下のようなことに気を付けて生活してみてください。
また、職場では共有洗剤や手袋を個人用に変えることも効果的です。
慢性化している場合は、「一時的に水仕事を控える」「業務内容を調整する」などの対応が必要になることもあります。

お子さまや高齢のかたの手湿疹は、皮膚の構造や生活環境の違いにより、成人とは異なる特徴と注意点があります。以下に、それぞれの年齢層における対応を詳しく説明します。
保湿を「こまめに・やさしく」
洗浄の工夫
掻き壊しの防止
学校生活での配慮

皮脂の代わりに保湿を補う
刺激の少ない生活環境づくり
軟膏の塗布サポート
感染予防と清潔管理
他疾患との関係
お子さまも高齢のかたも「皮膚バリア機能の低下」が根本原因です。そのため、保湿+刺激を避ける+医師の治療の3本柱は共通であり、年齢や生活環境に合わせて、無理のない継続ケアが大切になってきます。

手湿疹は、皮膚のバリアが壊れることで外的刺激に反応しやすくなり、炎症を繰り返す慢性疾患です。
薬で炎症を抑えるだけでなく、保湿と生活習慣の見直しを並行して行うことが再発防止の鍵となります。
「手のケアは毎日の積み重ね」です。早めに正しい治療を行い、自分の皮膚を守る習慣を身につけることで、手湿疹のない快適な生活を取り戻すことができます。
当院では、お子さまからおじい様、おばあ様もご一緒に通院できる病院です。何かありましたら、直ぐに当院までお知らせください。
医療法人社団涼美会理事長・形成外科医:関口 知秀
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-14:00 | ● | 休 | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
| 16:00-21:00 | ● | 休 | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
◯ 10:00-14:00 16:00-20:00
※当院は完全予約制ではございません。初診の方もご予約なしでの診察可能です。
【2月の休診日】2026年2月21日(土)、24日(火)、25日(水)、26日(木)
【午前のみ休診】17日(火)、24日(火)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
| 16:00-21:00 | ● | ● | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
◯ 10:00-14:00 16:00-20:00
※当院は完全予約制ではございません。初診の方もご予約なしでの診察可能です。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-14:00 | ● | 休 | ● | 休 | ● | ◯ | ◯ |
| 16:00-21:00 | ● | 休 | ● | 休 | ● | ◯ | ◯ |
◯ 10:00-14:00 16:00-20:00
※当院は完全予約制ではございません。初診の方もご予約なしでの診察可能です。