BLOGブログ

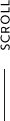
.jpg)
かゆみだけが主な症状として現れる「皮膚掻痒症」。湿疹や発疹がなくても強いかゆみに悩まされることがあり、生活の質(QOL)を大きく低下させます。そのため、高齢者や糖尿病、腎臓・肝臓の病気を持つ人では特に注意が必要です。本記事では、皮膚掻痒症の原因、メカニズム、治療、予防方法まで詳しく解説します。
「皮膚掻痒症(ひふそうようしょう)」とは、皮膚に明らかな発疹・湿疹・炎症を認めないにもかかわらず、持続的または反復的にかゆみが生じる状態を指します。
一般的な皮膚疾患と違い、通常の「かゆみ」とは、皮膚に明らかな発疹やアレルギー反応・皮膚疾患を伴うことが多いです。
一方で、皮膚掻痒症では発疹の目立たないケースが多く、その結果、原因が皮膚そのもの以外にあることも少なくありません。
慢性化すると、強く皮膚をかきむしるようになり、色素沈着・皮膚肥厚(ひふひこう)・二次感染といった深刻な症状に移行していきます。
さらに、かゆみというのは、不眠・ストレス・日常生活制限といったQOL低下に直結しますので、仕事や勉強の効率の低下にもつながってしまいます。
※参照URL:皮膚瘙痒症診療ガイドライン 2020
皮膚掻痒症では、次のような特徴がよく認められます。
かゆみが全身にわたって、あるいは特定部位(背中・四肢・頭部・陰部など)に出現することがあります。夜間・入浴後・温まったときなどに悪化しやすい傾向があります。例えば、皮膚が温まることで血流や神経刺激が高まり、かゆみを誘発することがあります。かいてしまうことによって、「掻破痕(そうはこん)=引っ掻いた跡」や「色素沈着」「皮膚肥厚」「苔癬化(たいせんか)(※1)」などが二次的に発生することがあります。
かゆみが6週間以上またはぶり返す場合は「慢性掻痒(まんせいそうよう)」とよばれ、原因を突き止めることが大切になります。かくことを我慢できない、またはかいた後もかゆみが続く、というような神経過敏の要素を伴うこともあります。
このように、こうした症状パターンを把握することで、単なる乾燥・かゆみとは異なる「皮膚掻痒症(ひふそうようしょう)と診断されることがあります。かゆみが続くと思われるかたは、お早めに当院までご連絡ください。早期発見・早期治療がカギになります。
※1「苔癬化(たいせんか)」とは、皮膚が慢性的に刺激を受けることにより、厚く、硬くなり、表面に深い溝や折れ目が現れる状態を指します。苔癬化とは皮膚肥厚の進行した状態を表します。
※参照URL:Chronic Pruritus: A Review | Dermatology | JAMA
※参照URL:皮膚瘙痒症診療ガイドライン 2020

まず、皮膚掻痒症は「外的要因」と「内的要因」が複合して起こります。一般的に、両者が複合して関与していることが多いため、原因を一つに限定せず総合的に捉えることが重要です。
当院では、皮膚科医が患者さまの状態に合わせた診察や治療を行います。
外的要因だけの場合もありますが、特に高齢者などではこれらが契機となって内的要因が現れることも少なくありません。
このように、皮膚そのものだけでなく、皮膚以外に起因するさまざまな因子が「かゆみ」に関与しているため、「単に保湿すれば治る」と考えると原因を見逃す危険があります。
※1:かゆみ閾値(いきち)とは、かゆみを感じ始める最小の刺激の強さを表し、高齢者はその閾値が低くなり、些細な刺激でもかゆみを感じやすくなります。
※参照URL:汎発性皮膚瘙痒症診療ガイドライン
※参照URL:Chronic Pruritus: A Review – PubMed
かゆみが生じるメカニズムは完全には解明されていません。けれども、近年の研究では皮膚・神経・免疫・内臓系が複雑に相互作用していることが明らかになっています。つまり、単一の要因では説明できない多層的な病態です。
かゆみを伝える神経線維(しんけいせんい)としてC線維(細径無髄線維(さいけいむずいせんい))が関与し、末梢(まっしょう)から中枢(ちゅうすう)へと刺激が伝わります。
過敏化した神経終末(しんけいしゅうまつ)はわずかな刺激でもかゆみとして認識されます。
ヒスタミンは古典的なかゆみのメディエーター(仲介者または媒介者)です。
それ以外にも、慢性的なかゆみではサイトカイン(※1)(例:IL-31)や神経ペプチド、トランスミッターの関与が注目されています。
特に乾燥や洗浄過多で皮膚バリアが低下すると、外部刺激が侵入しやすくなります。
同時に、神経終末が露出または活性化され、かゆみの閾値(いきち)が低くなりかゆみを感じやすくなります。
皮膚からの刺激が慢性化すると、中枢神経系が「かゆみ信号」に対して過剰反応を起こすようになってしまいます(感作)。
例えば、内臓性掻痒(ないぞうせいそうよう)(腎・肝疾患関連など)では、末梢だけでなく中枢での伝達・調節機構の変化も関与しています。
加齢による末梢神経線維(まっしょうしんけいせんい)の変性、μオピオイド/κオピオイド受容体のバランス変化(掻痒促進方向へ働く可能性)など、最新研究では新たな因子も提唱されています。
このように、皮膚掻痒症では「かゆみ」という単一の症状が、皮膚-神経-免疫-内臓系といった複数レベルの異常から生じていることから、原因が明確でないことも少なくありません。
※1:細胞から分泌されるたんぱく質です。多くの種類があり、細胞の増殖、分化、細胞死などを制御します。特に、免疫システムにおいて、免疫細胞を特定の場所に集めたり、免疫系を活性化したりする司令塔のような働きをします。
※参照URL:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38809527/
※参照URL:https://www.jaad.org/article/S0190-9622%2824%2900975-7/fulltext

では、診断の流れを見ていきましょう。皮膚掻痒症の診断では、まず「発疹・湿疹など明確な皮膚病変がない」ことを確認する上で、詳細な問診と身体所見が重要です。
その上で原因を探索するための検査を実施します。ただし、患者さまの症状によりその検査は異なりますので、全てのかたが同じ検査をするわけではありません。
かゆみの発症時期、部位、持続・頻度、夜間の悪化・入浴後の増強などを確認します。既往歴(腎・肝疾患、糖尿病、甲状腺疾患、血液疾患、精神疾患など)などのヒアリングを行います。現在使用中の薬剤(降圧薬・利尿薬・免疫療法薬・化学療法薬など)や妊娠・ホルモン変動の有無を確認します。生活環境(乾燥・暖房・衣類・洗剤・入浴回数)やストレス・睡眠状況も併せて確認します。
明らかな発疹・湿疹・紅斑がないか、掻破痕・色素沈着・皮膚肥厚(苔癬化)がないかをチェックしていきます。部位が特定されているか(例:背部・肩甲骨間・頭部など)も観察いたします。
血液検査:肝機能・腎機能・糖代謝・甲状腺ホルモン・血算(貧血・多血症)・血清鉄・アルブミン・電解質などを基本に診断を行います。必要に応じて、皮膚生検・神経学的評価・悪性腫瘍スクリーニングを行うこともあります。特に原因不明の慢性かゆみでは、より専門的な検査を行います。
発疹を伴う皮膚疾患(アトピー性皮膚炎・乾癬(かんせん)・蕁麻疹(じんましん)・接触皮膚炎など)かどうか精査します。かゆみが内臓疾患・薬剤性・神経性などに伴う可能性を考慮し、「掻痒症(そうようしょう)」すなわち発疹(ほっしん)を伴わないかゆみかどうかチェックします。
睡眠障害・日常生活の制限・心理的影響(ストレス・うつ)など、かゆみの影響度を定量的・定性的に評価していきます。当院では患者さまのお悩みに寄り添い診察していきますので、何かあれば気兼ねなくお伝えください。
診断のポイントは、「見た目にはあまり変化がないのに、かゆみという強い症状を訴える」というポイントです。
また、根本原因を探索しながら「対処療法(たいしょりょうほう):症状を和らげたり、一時的に取り除いたりする治療法」だけでなく「根本療法」の方向性も併せて診察していきます。
※参照URL:Diagnosis and Management of Chronic Pruritus
※参照URL:Chronic Pruritus: A Review | Dermatology | JAMA
※参照URL:Chronic Pruritus: A Review – PubMed

皮膚掻痒症の治療は、大きく「原因治療」「対症療法」「生活習慣・スキンケア改善」の三本柱で構成されます。
原因となる内臓疾患(腎・肝疾患・糖尿病・甲状腺疾患など)が判明した場合には、まずそれを適切に治療することが優先されます。かゆみが症状として出ている以上、原因の改善がかゆみ軽減のカギとなります。薬剤性のかゆみの場合には、担当医と相談のうえで処方箋の変更・中止を検討いたします。加齢性や神経性・精神的要因が関与する場合には、神経科・皮膚科・精神科など連携によるアプローチしながら治療を行います。
皮膚バリアを整えるために、セラミド・尿素など保湿成分を含むクリーム・ローションを毎日使用することが基本です。
乾燥がかゆみを誘発・悪化させるため、早期から実施すべきです。
外用薬:ステロイド外用薬(例:ヒドロコルチゾン2.5%、トリアムシノロン0.1%など)は、炎症を伴うかゆみで第一選択肢になることがあります。
※ステロイド薬は医師の指示に従い使用すれば、危険性は少なくかゆみも早く治ります。
非ステロイドの外用薬(カプサイシン、メントール・冷却系製剤、カルシニューリン阻害外用薬など)も、神経性成分・刺激低減を目的として用いられます。
※参照URL:皮膚瘙痒症診療ガイドライン 2020
※参照URL:Chronic Pruritus: A Review – PubMed
※参照URL:Therapeutics in chronic pruritus of unknown origin
室内湿度を40〜60%程度に保つことで乾燥を防ぎ、かゆみの誘発を抑えます。入浴時はぬるめ(38〜40℃程度)のお湯に入るようにし、長風呂・熱湯・強くこするような洗い方を避けることが望ましいです。
洗剤・柔軟剤は低刺激・無香料タイプを選び、衣服は綿・シルクなど肌に優しい刺激性の少ない素材をおススメします。爪を短めに切り、かゆみを感じたら積極的に冷却(冷タオル・冷風)を用いるなど「かかない工夫」を取り入れてみましょう。
栄養バランス(ビタミンA・E・オメガ3脂肪酸など)・規則的な睡眠・軽い運動・ストレス管理によって皮膚・神経系の健全性を保つことも重要です。精神的・神経的ストレスがかゆみを促進することがあるため、適度なリラクゼーション・入浴習慣・睡眠環境整備も有効です。
以上のように、治療は単一のアプローチではなく、原因除去+対症療法+スキンケア・生活習慣改善を組み合わせることが基本となります。

年齢層によって“かゆみ”の背景・ケアのポイントには少しずつ違いがあります。以下、代表的な高齢者・子どもについて整理します。
高齢になると、皮膚の水分保持能力・脂質分泌量が低下し、皮膚バリアが弱くなります。これが“乾燥→かゆみ”の典型的なパターンです。また、慢性疾患を有している・多剤併用しているケースが多く、薬剤性・内臓性の掻痒を併発していることが少なくありません。高齢者における「加齢性掻痒症(かれいせいそうようしょう)」では、末梢神経線維変性(まっしょうしんけいせんいへんせい)や中枢神経系が変化した可能性も指摘されています。ケアの重点としては、まず“乾燥対策”が挙げられます。保湿剤をこまめに使用する、室内湿度を保つ、刺激の少ない衣類を選ぶなどが有効です。かゆみによる掻破(そうは)で皮膚感染を起こしやすいので、かき壊し予防も非常に重要です。
お子さまでは、アトピー素因を持つ場合や乾燥肌傾向がある場合に、皮膚掻痒が発症または増悪しやすいです。かき壊し→二次感染(例えばとびひや細菌感染)という流れになりやすいため、早期保湿(そうきほしつ)・かかない工夫・皮膚の清潔を保つことが重要です。お子さまに関しては「夜間かゆみ→睡眠障害→生活リズムの乱れ」というサイクルに陥りやすいので、入浴・睡眠・皮膚ケアの生活習慣を整えることも治療の一環となります。特に発疹(ほっしん)を伴わないかゆみの場合、「ただの乾燥」か「掻痒症(そうようしょう)か」の判断を明確にすることが望まれます。
皮膚掻痒症(ひふそうようしょう)は、発疹が目立たないにもかかわらず、強いかゆみという症状が長期にわたって続くことで、日常生活や睡眠・心理状態に大きな影響を与える疾患です。
原因は皮膚そのものだけでなく、皮膚の保護機能低下(ほごきのうていか)・神経過敏化(しんけいかびんか)・内臓疾患・薬剤性・年齢変化など多岐にわたります。
診断にあたっては問診・身体所見・検査を通じて原因を探るとともに、治療では原因除去・対症療法・生活習慣改善を三本柱とした総合的アプローチが重要です。
特に、毎日の保湿や環境整備、かかない工夫を早期から始めることで、症状改善・再発防止に大きな効果を発揮します。
かゆみが長引くようであれば、放置せず、当院皮膚科医にお早めにご相談ください。
医療法人社団涼美会理事長・形成外科医:関口 知秀
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-14:00 | ● | 休 | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
| 16:00-21:00 | ● | 休 | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
◯ 10:00-14:00 16:00-20:00
※当院は完全予約制ではございません。初診の方もご予約なしでの診察可能です。
【2月の休診日】2026年2月21日(土)、24日(火)、25日(水)、26日(木)
【午前のみ休診】17日(火)、24日(火)
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
| 16:00-21:00 | ● | ● | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
◯ 10:00-14:00 16:00-20:00
※当院は完全予約制ではございません。初診の方もご予約なしでの診察可能です。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-14:00 | ● | 休 | ● | 休 | ● | ◯ | ◯ |
| 16:00-21:00 | ● | 休 | ● | 休 | ● | ◯ | ◯ |
◯ 10:00-14:00 16:00-20:00
※当院は完全予約制ではございません。初診の方もご予約なしでの診察可能です。