
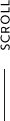

アトピー性皮膚炎は乳幼児から成人まで幅広い年代に見られる慢性皮膚疾患であり、生活の質(QOL)に大きく影響する疾患として知られています。ここでは、アトピー性皮膚炎とはどのようなものなのか、そのメカニズムや症状、診断、治療の方法、日常生活で工夫できることなどを紹介いたします。お悩みの方や皮膚に違和感を感じた方は、早めに当院までご連絡ください。
アトピー性皮膚炎とは実際にどのようなものなのでしょうか。ここでは、日本皮膚科学会が定めた定義、疾患の特徴、疫学データ、社会的インパクトなどのお伝えします。
アトピー性皮膚炎(Atopic Dermatitis, AD)は、強いかゆみを伴う慢性・再発性の湿疹を特徴とする炎症性皮膚疾患です。日本皮膚科学会の診断基準では、以下のような特徴を持つことが必須項目として示されています。
※参照URL:日本皮膚科学会ガイドライン
最新のデータによれば、日本におけるアトピー性皮膚炎(atopic dermatitis)の患者数は、厚生労働省の定点調査によると約45万人と推測されています。
小児期:厚生労働省の調査では、4ヶ月児で12.8%、3歳児で13.2%、小学1年生で11.8%と、全体的に10〜15%程度の有症率が示されています。
成人:近畿大学病院のデータによると、20歳代で10.2%、30歳代で8.3%、40歳代で4.1%、50〜60歳代で2.5%など、年齢が上がるにつれて割合が減少する傾向が見られます。
注:これらの割合は調査対象や時期によって変動する可能性があり、小児期に比べて成人では症状が軽くなるケースもあるため、年齢によって有症率に差が生じることもあります。
世界的な観点からすると、日本のアトピー性皮膚炎患者数は少ないですが、それは、日本人がアトピー性皮膚炎になりにくいからではありません。
日本の皮膚科医療は世界でもトップクラスの水準であり、治療率の高さやその質の良さにより、アトピー性皮膚炎の割合を抑えているためです。
※参照URL:Atopic dermatitis: A global health perspective – PubMed
※参照URL:アトピー性皮膚炎の病態と治療の最前線
※参照URL:アレルギー疾患疫学調査文献データベース
強いかゆみと睡眠障害:夜間のかゆみで眠れず、日中の眠気・集中力低下につながります。お子さまに関しては、学習成績や学校生活への支障が出やすくなります。
また、成人の方では仕事の生産性低下(仕事の効率や集中力、または対人関係への不安)が起こりやすくなることが分かっています。
慢性疾患としての負担:アトピー性皮膚炎が慢性的になると、数年〜数十年と続くことがあり、長期にわたる治療とセルフケアが必要になります。
※注:アトピー性皮膚炎は感染症皮膚疾患ではありません。ですので、家族や周囲にはうつりません。
小さなお子さまの場合、夜間のかゆみで家族の睡眠も妨げられ、家族全員の生活リズムに影響を及ぼすこともあります
体育・水泳・校外活動の制限が必要になる場合もあり、学校側の理解と配慮が不可欠になります。
外見・症状のため接客業や特定の職種に就きにくいと感じる方もいらっしゃいます。
アトピー性皮膚炎は単に「皮膚のかゆみの病気」ではなく、患者さま本人の生活の質を大きく下げ、教育・就労・医療費・社会参加にまで広く影響を及ぼす疾患です。アトピー性皮膚炎かもしれないと感じたら、当院までお早めにご連絡ください。
定義の項目でもお伝えした3大特徴のほかにも、以下のような特徴を持ち合わせているのがアトピー性皮膚炎です。
強いかゆみを伴い、夜間に悪化することもある。掻くことでさらに炎症・湿疹が悪化する「かゆみ→かき壊しの悪循環 (itch‐scratch cycle)」が特徴です。
湿疹には、紅斑/丘疹/水疱/浸出液/かさぶた/鱗屑(りんせつ)など、湿疹の形態が段階に応じて変化します。
<>慢性期(乳児で2ヶ月以上、その他の年齢では6ヶ月以上の期間を経たもの)には苔癬化(皮膚が厚く硬くなる)が見られることもあります。
また症状が一旦治まっても、季節変動・刺激物やストレス・アレルゲンの暴露などで再発しやすくなります。
汗や皮脂、角質層(何層にもなっている皮膚の一番表面の層)など、私たちの皮膚は外部刺激から守られるように、さまざまなバリアを張り巡らしています。
アトピー性皮膚炎では、その角質層のバリアが弱く、肌を守る力が弱いことにより、アレルゲンや刺激物が侵入しやすくなり引き起こされます。
Th2 細胞(ヘルパーT細胞2型)とは、外部からの刺激(アレルゲンや細菌、寄生虫など)から体を守るための「液性免疫(えきせいめんえき)」を担うT細胞の一種です。
このTh2細胞の指令によりサイトカイン(IL-4, IL-5, IL-13, IL-31 等)などの情報伝達のためのタンパク質が異常に増え、かゆみや腫れなどの炎症を直接または間接的に過剰に引き起こします。
年齢によってもアトピー性皮膚炎の特徴は異なります。
最新のデータによれば、日本におけるアトピー性皮膚炎(atopic dermatitis)の患者数は、厚生労働省の定点調査によると約 45 万人と推測されています。
日本人のアトピー性皮膚炎の割合自体は決して少ないわけではありません。しかし、世界的な観点からすると、日本はアトピー性皮膚炎の患者数は少数に分類されています。
それは、日本の皮膚科医療が世界でもトップクラスの水準であり、治療率やその質の高さにより、アトピー性皮膚炎の割合を抑えているからです。
※参照URL:Atopic dermatitis: A global health perspective – PubMed
※参照URL:2)アトピー性皮膚炎の病態と 治療の最前線
※参照URL:アレルギー疾患疫学調査文献データベース
アトピー性皮膚炎の患者さんの多くは、家族に 喘息・花粉症・アレルギー性鼻炎などの「アレルギー体質(アトピー素因)」を持つ方がいます。
これは遺伝的にアレルギーを起こしやすい体質が受け継がれるためです。
また、フィラグリン遺伝子異常も遺伝的要因の1つです。皮膚のバリア機能に重要なタンパク質「フィラグリン」を作る遺伝子に異常があると、角質が弱くなります。
角質層は一般的に「皮膚」とよばれている部分であり、表面をカバーしています。この角質層が乾燥しやすくなると、外からの刺激やアレルゲンが入り込みやすくなることが分かっています。
アレルゲンの存在はアトピー性皮膚炎の主な要因になっています。家の中の ダニ・ハウスダスト(ほこり)・ペットの毛・花粉・食物などは私たちの皮膚から侵入し、免疫系を刺激して症状を悪化させます。
また、生活や気候にも影響されます。例えば、空気の乾燥は皮膚の水分が失われやすく、冬の寒さや湿度の変化は皮膚の保護バリアが不安定となり、アトピー性皮膚炎を悪化させます。
は自律神経やホルモンバランスを乱し、免疫の働きに影響を及ぼすため、アトピー性皮膚炎になるきっかけや悪化の原因になります。
私たちの体には「免疫」という防御システムがあり、細菌やウイルスから体を守っています。免疫にはいくつかのタイプがあり、その中に Th1と Th2という2つのチームがあります。
本来はこの2つのバランスが大事なのですが、アトピー性皮膚炎の患者さまでは Th2チームが強く働きすぎる(=Th2優位) 状態になってしまいます。
このTh2チームが過剰に働き出すと「IgE」というアレルギー反応に関わる抗体を通常よりも多く増やしてしまうため、ダニや花粉などに異常に過敏に反応してしまいます。
本来ならば私たちの体を守る免疫が、働きすぎると皮膚の炎症とかゆみを引き起こしてしまい、アトピー性皮膚炎になるのです。
※治療薬(ステロイド、免疫抑制薬、生物学的製剤など)は、この「Th2の働きすぎ」を抑えることが目的で使用されています。
アトピー性皮膚炎は角質層の水分保持低下でもなってしまう可能性があります。
例えば、皮膚の一番外側である角質層が水分を保てないため、乾燥してカサカサになりやすくなります(冬のかかとやひじ・ひざを思い出してみてください)。
その角質層のバリアが壊れてしまった結果、健康な皮膚なら入ってこない アレルゲン・細菌・化学物質 が侵入しやすくなり、炎症や炎症の悪化を引き起こしてしまいます。
また、上記のサイクルが「免疫の暴走」を助長し、慢性的な湿疹の原因にもなってしまいます。
ここでは、日本皮膚科学会と厚生労働省が定めている治療ガイドラインに基づいた診断ガイドラインをお伝えします。
※参照URL:アトピー性皮膚炎診断ガイドライン
アトピー性皮膚炎の診断は、以下の項目を総合的に判断して行われます。
これらを総合的に満たすと「アトピー性皮膚炎」と診断されます。
※当院では皮膚科医が診断を行います。何かご相談があればお早めに当院までご連絡ください。
似たような皮膚症状を示す病気も多いため、誤診を避けるための鑑別(本当にその病気なのか、それとも他の病気なのかを区別して見極めるために考慮する病気のこと)が必要です。
アトピー性皮膚炎は「完治する」病気ではなく、症状をコントロールし、生活の質(QOL)を高めることが治療の目標です。そのために、薬物療法・スキンケア・生活指導・患者教育の3本柱が重要になります。
※参照URL:アトピー性皮膚炎の治療ガイドライン(p18から)
眠気が出る薬もあるので、患者さまの生活に合わせて選択できます。当院では眠気の出にくい薬も処方できますので、医師にお伝えください。
入浴後5分以内に全身に塗布してください。乾燥を防ぎ、バリア機能を守ります。
石けんは刺激の少ないものを少量使用しましょう。洗いすぎは逆効果です。
お子さまに関しては、睡眠時は手袋や肘カバーを使うのも有効です。
カーテンなど洗える素材は定期的に洗いましょう。パネルカーテンなどは定期的に拭き取り清潔にするのもおすすめです。
「強い薬だから怖い」というイメージが広がっていますが、医師の指示通りに正しく使えば安全性はむしろ高く、かゆみや腫れなどの症状が早く改善します。
むしろ中途半端な使用が再発や副作用を招きますので、自己判断は絶対に止めてください。
症状が改善しても自己判断で中止せず、医師の指導のもとで徐々に使用を制限していくことが大切です。
早めに再診し、薬を正しく再開することで重症化を防ぎます。お忙しいとは思いますが、酷くならないためにも、早めのご来院をお願いします。
綿素材や通気性のよいものを選び、ウールや化繊は避けましょう。
また、お子さまで多いのですが、タグなどの縫い目が痒みを引き起こす場合もあります。その場合には、タグを切り取る、またはタグがプリントされているような衣服を選びましょう。
また、汗をかいたらタオルで汗を拭きとるか、こまめに着替えるようにしましょう。予備の着替えを用意しておくのもおすすめです。
特定の食物アレルギーがある場合は、その食品のみを除去しましょう。根拠のない過度な食事制限は栄養不良を招きますので、注意してください。
アトピー性皮膚炎はストレスによっても起きやすくなります。ストレスは悪化因子のひとつです。そのため、睡眠の質を改善し、適度な運動を取り入れるようにしましょう。
冬:加湿器を使って乾燥を防ぎましょう。静電気も肌には刺激ですので、保湿ケアに力を入れましょう。 夏:汗を早めに拭き取り、シャワーで清潔を保ちましょう。アトピー性皮膚炎の方は日焼け止めなども肌に合わない場合があります。その際には、医師に直ちにご相談ください。 春・秋:花粉症などのアトピー性皮膚炎以外のアレルギー症状も起こりやすくなる季節です。何かアレルギー症状が起きた場合には、医師に連絡し早めの対処をしてください。 アトピー性皮膚炎は「皮膚の病気」であると同時に「生活全体に関わる病気」です。 また、医師の診断だけでなく、患者さまに合わせた適切な薬物療法、日々のスキンケア、そして患者さま自身やご家族の理解と協力が揃うことにより症状を安定させ、快適な生活を送ることができます。 当院では皮膚科医が一人ひとりの患者さまに合わせた治療を行います。何かお困りの際には、お早めに当院までご相談ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-14:00 | ● | 休 | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
| 16:00-21:00 | ● | 休 | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
◯ 10:00-14:00 16:00-20:00
※当院は完全予約制ではございません。初診の方もご予約なしでの診察可能です。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-14:00 | ● | ● | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
| 16:00-21:00 | ● | ● | ● | ● | 休 | ◯ | ◯ |
◯ 10:00-14:00 16:00-20:00
※当院は完全予約制ではございません。初診の方もご予約なしでの診察可能です。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-14:00 | ● | 休 | ● | 休 | ● | ◯ | ◯ |
| 16:00-21:00 | ● | 休 | ● | 休 | ● | ◯ | ◯ |
◯ 10:00-14:00 16:00-20:00
※当院は完全予約制ではございません。初診の方もご予約なしでの診察可能です。